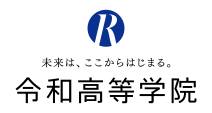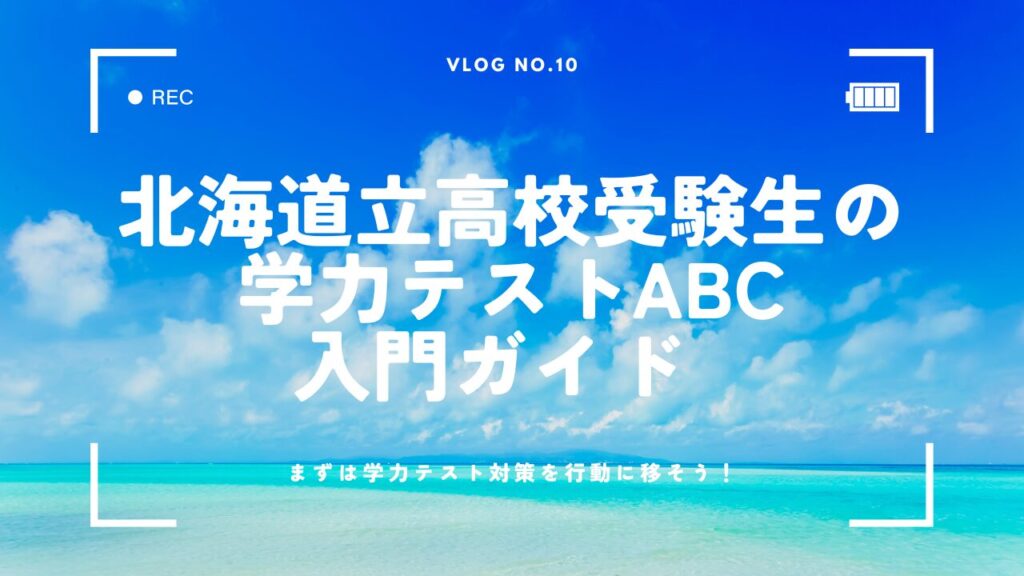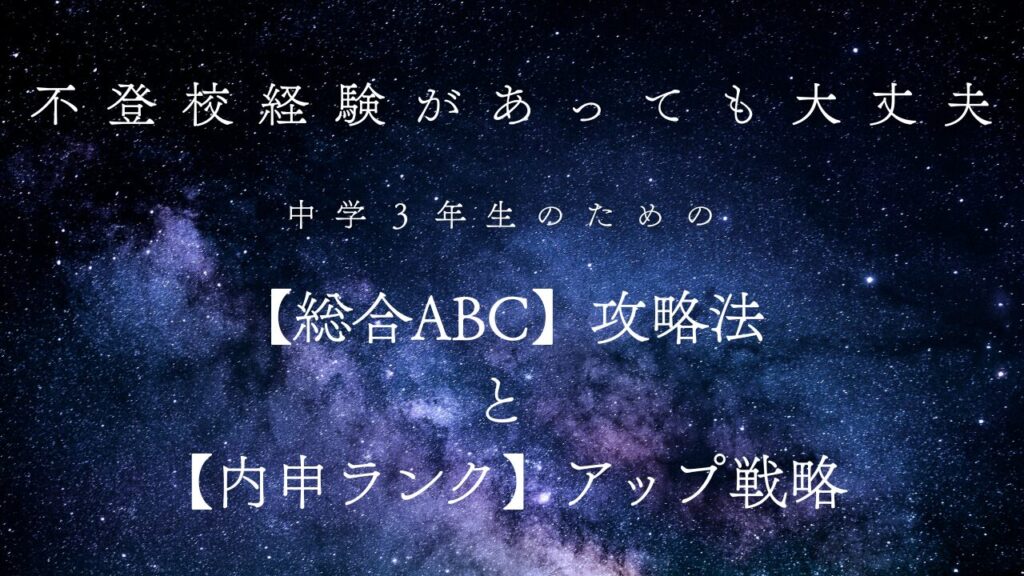
はじめに:君の「今」が未来を創る!不登校経験があっても諦めないで
中学3年生にとって、9月から始まる「学力テストABC」は、高校受験に向けてとても大切な試験です。
このテストは、北海道の高校受験で進路を大きく左右する重要なポイントとなります。
特に、これまで学校にあまり通えなかった生徒にとっても、「今から」の努力が未来を作るうえで決定的に大切です。
学力テストABCは、努力が目に見える成果として現れる大きなチャンスです。
この記事では、学力テストABC(通称「総合ABC」)の攻略法と、高校入試で重要な「内申ランク」との関係について、実践的な情報を詳しく紹介します。
過去のことにとらわれず、今できることに集中することが大切です。
このテストは、自分の学力を客観的に知るための道しるべであり、新しいスタートを切るための貴重な機会となります。
学力テストABCは、単なる学力測定だけでなく、さまざまな意味を持っています。
特に不登校経験のある生徒にとっては、自己肯定感を取り戻し、これまでの学習の空白を客観的に知り、未来への一歩を踏み出すための大切な手段となります。
学校に十分通えなかった生徒は、自分の学力に自信が持てないことも多いですが、このテストで「今の自分の実力」を知ることで、漠然とした不安を減らし、具体的な目標を立てることができます。
小さな成功体験を積み重ねることは、自己肯定感を高めるうえでとても効果的です。 また、不登校期間中に学習が遅れていた場合でも、テスト結果からどの分野に大きな穴があるのかをはっきり知ることができます。

これは、やみくもに勉強するのではなく、効率よく学習計画を立てるために欠かせない情報です。
学力テストABCの結果は、冬休み前の三者面談で志望校を決めるときの大切な資料にもなります。漠然とした不安を持つ生徒にとって、具体的な進路選択への大きな後押しとなるでしょう。 つまり、「総合ABC」は、学力を測るだけでなく、心の支えとなり、具体的な学習戦略を立てるための大切なツールです。
2. 学力テストABCってどんなテスト?基本を知ろう!
学力テストABCは、北海道教育文化協会が主催し、北海道内のすべての中学校で同じ日に一斉に行われます。毎年、中学3年生を対象に9月に学力テストA、10月にB、11月にCが実施されます。
この時期は、高校受験に向けて学力を伸ばす大事なタイミングです。 このテストの目的は主に4つあります。
1つ目は、自分の学力を客観的に知り、現実的な志望校を決めるための道しるべになること。
2つ目は、中学3年間の学習内容をすべてカバーする3回の試験で、これまでの理解度を総合的に確認できること。
3つ目は、公立高校入試と同じ形式で出題されるため、本番の入試に慣れる練習になること。
4つ目は、テスト結果から自分の得意・不得意分野を知り、今後の学習計画を立てるための診断ツールになることです。
学力テストABCは、国語・社会・数学・理科・英語の5教科で、各教科100点、合計500点満点です。これは実際の高校入試と同じ形式です。各教科の試験時間は50分です。
【学力テストABCの概要】
・実施時期:A(9月)、B(10月)、C(11月)
・主催:北海道教育文化協会
・対象:中学3年生
・教科:国語、社会、数学、理科、英語(各教科リスニング含む)
・配点:各100点、合計500点
・試験時間:各50分
・目的:志望校決定の資料、実力把握、入試形式への慣れ、得意・不得意の把握
・内申点への影響:直接反映はないが、志望校決定の資料として使われる
「内申ランク」(学習点)と「総合ABC」(学力点)の関係
学力テストABCの成績は、中学校の通知表に記載される内申点(学習点)には直接反映されません。
しかし、北海道の公立高校入試では、入試当日の学力検査(学力点:5教科500点満点)と、中学3年間の通知表から計算される学習点(内申点:315点満点)の両方が合否判定に使われます。
どちらも大切なので、両方をしっかり意識しましょう。 学習点は、9教科の通知表の合計から計算され、1年生と2年生は2倍、3年生は3倍の重みで換算されます。副教科も主要5教科と同じ配点なのが北海道の特徴です。
学力テストABCは内申点には直接関係しませんが、学校によっては「校内推薦」の資料として使われることもあります。 不登校経験のある生徒は、1・2年生の内申点が低かったり、評価が厳しくなることがあります。
これは学習点で不利になることもあります。そのため、学力テストABCで高い点を取ることは、学習点の不足を補ううえでとても大切です。テストの点数は「今の実力」を測るもので、過去の出席状況には左右されません。

だからこそ、「学力テストABCで挽回する」という戦略はとても現実的で効果的です。 また、3年生の内申点は3倍の重みがあるので、今から学校生活に復帰し、日々の学習や提出物をしっかり行えば、内申点を上げることもできます。
副教科も主要5教科と同じ配点なので、実技教科での努力も合否に影響します。
不登校経験のある生徒は、学力テストABCで高得点を目指すだけでなく、3年生の内申ランク改善、特に副教科も含めた日々の学習にも取り組む「ハイブリッド戦略」が最も効果的です。
3. 【総合ABC】を攻略!科目別・テスト別対策のヒント
全体的な出題傾向と難易度 学力テストABCは、中学3年間の学習内容を幅広くカバーしています。1学期には各テストの出題範囲表が配られ、これが学習計画を立てるうえでとても大切な指針となります。
学力テストAやBでは、中学1・2年生の内容が多く出題されます。Cテストになると、中学3年生の内容が約3割含まれ、テストが進むにつれて最新の学習内容の比重が増えます。
公立高校入試本番と比べると、学力テストABCは難問が少ない傾向です。 この「難問が少ない」という特徴は、基礎学力に不安がある生徒でも、基礎からしっかり点数を積み上げて自信を取り戻すチャンスになります。
特にA・Bテストで中学1・2年生の基礎を徹底的に復習し、自信をつけることは、その後のCテストや入試本番で応用問題に挑戦する力につながります。基礎がしっかりしていれば、Cテストで増える中学3年生の範囲にもスムーズに取り組めます。
難しい問題ばかりだと心が折れやすいですが、基礎問題で得点できる喜びは、学習のやる気を保つうえでとても大切です。
各テストでは、科目ごとに難易度や出題傾向に違いがあります。以下は、学力テストABCの実施時期と出題範囲、難易度の目安です。
【テスト別の特徴】
・学力テストA(9月):中学1・2年生の内容が中心。理科は平均点が低く、情報整理力が必要。
・学力テストB(10月):中学1・2年生の内容が中心で、3年生の内容も追加。社会は易しめ、理科・英語はやや難しめ。
・学力テストC(11月):中学1・2年生の内容に加え、3年生の内容が約3割。数学や理科、国語・英語で3年生の内容が入試に近づく。
科目別出題傾向と対策のポイント
【国語】
学力テストBでは、北海道の高校入試を意識した問題が多く出ます。記述問題で部分点の減点が多いので、正解を覚えるだけでなく、自分の解答のどこが足りなかったか、文章のどこに注目すべきだったかを確認することが大切です。基礎的な語彙力や文法力をしっかり身につけ、「会話・発表問題」にも対応できるようにしましょう。
【数学】
学力テストABCでは、出題パターンや難易度に大きな変化はありません。安定して得点しやすい科目です。配点が高いので、計算ミスに注意しましょう。Cテストでは関数や確率が入試に近くなり、二次関数や相似など3年生の範囲は重点的に対策しましょう。まずは1・2年生の基礎を完璧にすることが大切です。
【社会】
社会は問題が読みやすく、AよりBの方が選択に悩む問題が少ない傾向です。周辺知識が大切で、単なる暗記ではなく深い理解が求められます。資料読解や記述問題が多く、これが得点差のポイントです。近現代史の問題が多いので、歴史の流れを整理しながら学習しましょう。
【理科】
学力テストAでは「台車の実験」や「エネルギーの移り変わり」「地層・岩石」がよく出ます。平均点が低い学校も多いので、知識を覚えるだけでなく、問題文から必要な情報を読み取り、論理的に考える力が必要です。Cテストでは「運動とエネルギー」の単元が出題され、速さや仕事の計算などの練習が大切です。実験の目的や方法、結果、考察を深く理解し、計算問題の演習を徹底しましょう。
【英語】
英語はリスニング、長文読解、英作文の3つに分かれます。長文読解が配点の約半分を占めるので、最優先で対策しましょう。CテストはBより難しくなり、文法や読解の難易度が上がります。Cテストでは関係代名詞も出るので、3年生で学ぶ文法をしっかり身につけましょう。北海道では毎年テーマ英作文が出るので、自分の知っている表現で文章を作る練習が必要です。英文和訳の練習も効果的です。
「不登校経験」を強みに変える!効果的な学習計画と実践術
1ヶ月ごとの学習計画の立て方
学力テストABCに向けては、1学期に配られる範囲表をもとに、A・B・Cそれぞれ1ヶ月ごとに計画を立てることが大切です。
広い範囲を段階的に消化するには、計画性が欠かせません。計画を立てずに勉強すると、効率が悪くなりがちです。 不登校経験のある生徒は、学習習慣が身についていなかったり、学習の空白期間があるため、計画なしで広い範囲をカバーしようとすると挫折しやすいです。

だからこそ、計画を立てること自体が学習への「足がかり」となり、日々のルーティン作りに役立ちます。ただし、体調や気分によって計画通りに進まないこともあります。そんなときは、計画通りにいかなかった自分を責めず、計画は「目安」として柔軟に修正することが大切です。
「今日はこの1単元だけ」「この問題集の1ページだけ」といった小さな目標を立てて、「できたこと」を積み重ねることで、自信と継続力が身につきます。
これは、学習へのハードルが高い生徒にも有効な方法です。 過去問の活用法と入手方法 過去問は学力テストABC対策にとても役立ちます。解いて終わりではなく、必ず解き直しをして、周辺知識や似た問題も解くことが大切です。
学力テストは毎年似た傾向があるので、過去問を解くことで本番で同じ形式の問題に対応しやすくなります。 過去問は学校の先生から配られることが多いですが、主催団体のウェブサイトには掲載されていません。
手に入らない場合は、北海道学力コンクール(道コン)事務局が提供する対策模試を利用するのも良い方法です。道コンの模試は学力テストABCを分析して作られており、本番に近い演習ができます。学習塾に通っていれば、過去問の入手や詳しい解説、個別指導も受けられます。
市販教材では「高校入試落とせない入試問題 5教科 5冊セット」がおすすめです。
テスト結果の分析と復習の大切さ 学力テストABCの結果は、その後の受験勉強にどう活かすかがとても大切です。

点数に一喜一憂するのではなく、できなかったところをしっかり確認し、補強することが重要です。
間違えた問題は、ケアレスミスなのか、解き方が分からなかったのか、原因を見つけることが効果的な対策の第一歩です。
解き方が分からなかった問題は、その単元に戻って復習し、「間違えた原因を探す→復習→似た問題を解く」というサイクルを大切にしましょう。できなかった問題をやり直すだけでなく、周辺知識も再確認し、類題も複数解くことで、知識がつながり、応用力が身につきます。
「中3範囲」の得点率に注目した学習戦略
学力テストCでは、「中学1・2年生の範囲」と「中学3年生の範囲」の得点率を計算してみることが大切です。
高校入試本番では、中学3年生の夏以降に学ぶ範囲が体感で6割以上を占めるとも言われています。この比重の大きさを理解しましょう。
中学1・2年生の範囲は復習に時間をかけやすく、点数も取りやすいですが、中学3年生の夏以降の範囲は短期間で「授業→基本を覚える→テストや入試レベルまで仕上げる」という流れが必要なので、得点しにくい傾向があります。
もし「中学3年生の範囲」の得点率が「中学1・2年生の範囲」より大きく低い場合は、今後の勉強の時間ややり方を見直す必要があります。
一人じゃない!外部リソースを上手に活用しよう
学力テストABC対策では、市販教材や学習塾、家庭教師などの外部リソースをうまく使うことが効果的です。特に公式の過去問が手に入りにくい場合は、これらのリソースを活用しましょう。
【市販教材の活用法】
「高校入試 落とせない入試問題 5教科 5冊セット」は、基礎から応用まで幅広くカバーしており、効率よく学習できます。
【学習塾の活用法】
学習塾では、学力テストABCの分析に基づいた模試や対策授業が受けられます。道コンと連携して合格可能性の算出や志望校決定の資料も提供され、客観的なデータに基づいた進路指導が受けられます。個別指導塾では、苦手分野の克服や得意分野の強化に役立ちます。
【家庭教師の活用法】
必要に応じて、家庭教師の無料体験授業などを利用するのも良い方法です。家庭教師は生徒の弱点に合わせた指導ができ、効率的な学習をサポートします。
【公式過去問が手に入りにくい場合】
主催団体のウェブサイトには過去問が掲載されていませんが、学習塾や道コン事務局が提供する模試を利用するのが有効です。道コンの模試は本番に近い演習ができます。
これらの外部リソースは、問題を解くだけでなく、間違えた原因を分析し、関連知識を広げ、似た問題で定着を図る深い学習サイクルをサポートします。
また、塾や家庭教師は、学力向上だけでなく、不登校経験のある生徒が感じやすい「学習の遅れへの不安」や「孤立感」「学習習慣の欠如」といった悩みにも、心理的な安心感やサポートを提供します。個別指導や少人数制の塾は、安心して質問できる環境や「自分だけを見てくれる」サポートとなり、学習意欲や精神的な安定にもつながります。
さらに、塾や家庭教師は、定期的な学習の機会を作り、学習ルーティンの再構築を助けます。宿題の管理や進捗の確認を通じて、自分で学習する習慣も身につきます。道コンとの連携による合格可能性の算出や志望校決定の資料提供は、進路選択の不安を客観的なデータで和らげてくれます。
【内申ランク】も意識!日々の学習が未来を拓く 内申点(学習点)の重要性
北海道の公立高校入試では、学力点(総合ABCの結果)と学習点(内申ランク)の両方が合否判定に使われます。
特に中学3年生の学習点は3倍の重みがあるので、今からの努力が大きく影響します。副教科(保健体育、美術、音楽、技術・家庭)も主要5教科と同じ配点なので、これらの教科も大切にし、授業態度や提出物、定期テストにしっかり取り組みましょう。

不登校経験がある生徒にとって、内申点の改善は難しく感じるかもしれません。しかし、3年生の成績が3倍の重みを持つということは、今からの努力で過去の評価を上回るチャンスがあるということです。これは、未来に向けて努力する大きなモチベーションになります。
日々の学習習慣の確立
学力テストABC対策を通じて、中学3年間の総復習ができます。これは高校受験勉強の大きな足がかりです。
自分の現在地を知り、効率よく勉強を進めることが大切です。 「わからなかった」からこそ、新しい発見があるという前向きな気持ちを持ちましょう。テストの解き直しや宿題への丁寧な取り組み、「さかのぼり学習」など、基本的な学習習慣が大切です。これらは短期的な成果だけでなく、長期的な学力向上にもつながります。
不登校経験のある生徒は、副教科は実技や提出物、授業への参加態度が評価に直結しやすいことを理解しましょう。
主要5教科だけでなく、副教科でも積極的に取り組むことで、比較的短期間で内申点を上げることができます。これは、学力テストの点数だけでは補えない部分をカバーする戦略です。
毎日学校に通うのが難しい場合でも、オンライン授業への参加や提出物の郵送、個別面談での学習進捗報告など、「できる範囲」で学校と連携を続けることが、教師からの評価(内申ランク)につながります。
完璧を目指すのではなく、小さな努力を続けることが大切です。学力テスト対策と並行して、「今できること」から内申点改善に向けて行動することで、高校入試での総合評価を高めることができます。
おわりに:自信を持って、君だけの未来へ!
北海道の高校受験を控える中学3年生にとって、9月から11月に行われる学力テストA・B・Cは、単なる学力測定以上の大切な機会です。
これらのテストは、自分の学力を客観的に知り、志望校を現実的に決めるための道しるべです。

また、高校入試本番の形式に慣れ、時間配分や問題への対応力を身につけるための貴重なシミュレーションの場でもあります。 不登校経験があっても、それは自分の「可能性」を狭めるものではありません。
学力テストABCは、どれだけ成長したか、これからどれだけ伸びるかを示す大切な指標です。結果に一喜一憂するのではなく、それを自分の学習課題を見つけ、改善するためのフィードバックとして活用しましょう。
日々の学習習慣を身につけ、困難に直面しても前向きに学び続ける強い心を育てることが、最終的な目標達成につながります。 学力テストABCへの取り組みと結果分析のプロセスは、不登校経験のある生徒が「自分にはできる」という自信を持ち、困難に直面しても立ち直る力(レジリエンス)を育てる貴重な機会です。
学習に自信を失っている生徒にとって、計画を立てて実行し、結果が出たときに「自分が努力すればできる」と感じることは、今後の学習だけでなく、人生全体の自信にもつながります。
たとえ点数が思うようにいかなくても、努力の過程や間違えた問題を分析して理解できたという小さな成功体験が、この自信を育てます。 また、テストで思うような結果が出なくても、「なぜ間違えたのか」を分析し、「どうすれば次はできるか」を考えることは、失敗から学び、立ち直る力を養います。
不登校経験のある生徒は、挫折経験が多いかもしれませんが、このレジリエンスを育てることは、受験期を乗り越えるうえでとても大切です。 「わからなかった」ことを恐れず、それを「新しい発見」として前向きに捉える姿勢は、学習を苦しいものから楽しいものへと変えることができます。
これは、学習に対してネガティブな気持ちを持ちやすい生徒にとって、学び続けるための大きな力になります。 学力テストABCを最大限に活用し、高校入試という大きな目標に向かって一歩ずつ進んでいきましょう。自信を持って、君だけの未来へ歩み出してください。